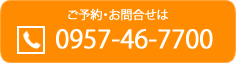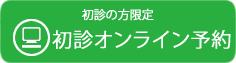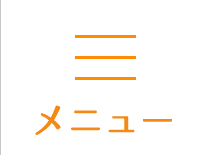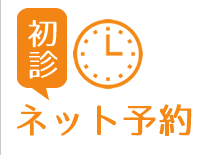こんにちは、長崎県諫早市の歯医者、諫早駅前歯科です。
毎日の歯磨きで使っている「歯磨き粉」。パッケージに「フッ素配合」と書かれているのを見たことがある方も多いのではないでしょうか。
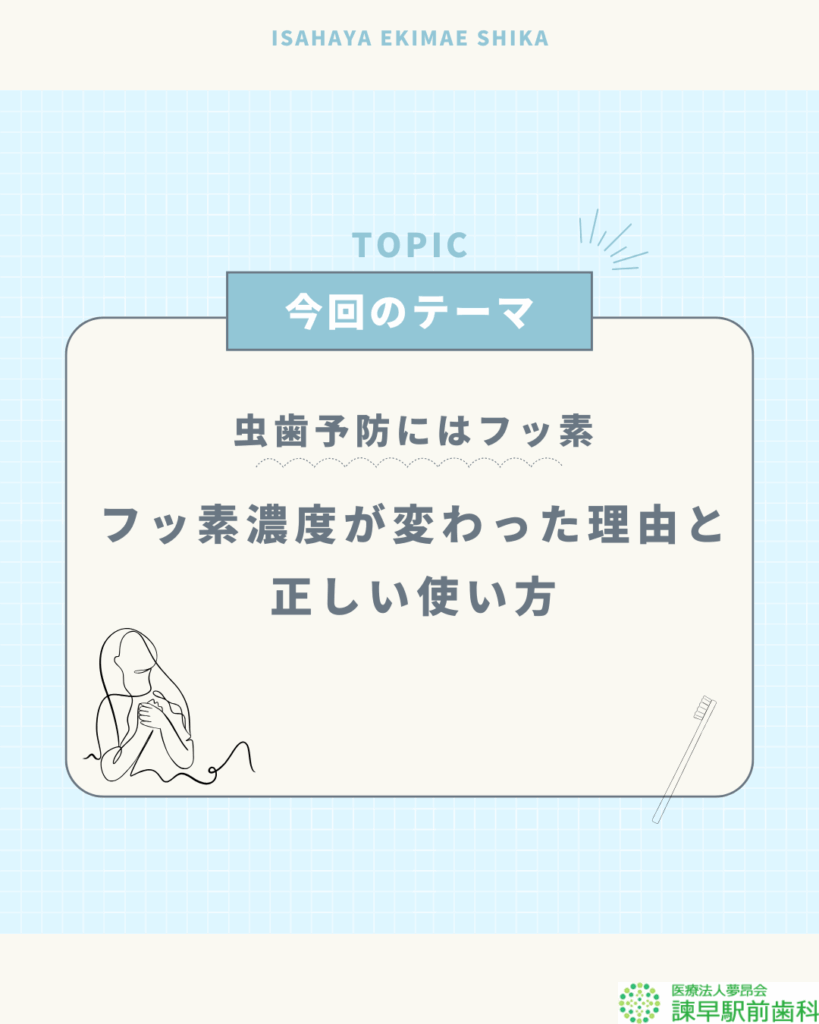
「なんとなく体に悪そう」
「子どもには使わないほうがいいのでは」
そんな不安を耳にすることもあります。しかし実際には、フッ素は世界中で虫歯予防に役立っている成分であり、日本でも安全性が確認された上で使われています。
さらに2023年には、歯磨き粉に含まれるフッ素の推奨濃度が年代ごとに見直されました。幼児期から高齢期まで、それぞれの年齢に合わせてより高い濃度が推奨されるようになり、虫歯予防を一層効果的に行えるようになったのです。
今回は、フッ素の働きと新しい濃度基準、そして年代ごとの使い分けやリスクについて、わかりやすくご紹介します。
目次
フッ素はなぜ虫歯予防に効くのか?
フッ素は自然界に存在する元素の一つで、特に歯の健康に深く関わっています。
その理由は次の3つです。
- 再石灰化を助ける
食事のたびに歯の表面からミネラルが溶け出します(脱灰)。フッ素は、その失われたミネラルを戻す「再石灰化」をサポートし、初期の虫歯を元に近い状態へと戻す働きをします。歯の再石灰化に関しては知っておきたい虫歯の進行と症状を参考にされてください。 - 歯を強くする
フッ素が取り込まれた歯は、酸に強い構造に変化します。これにより虫歯菌が出す酸に溶けにくくなり、虫歯の進行を防ぎます。 - 虫歯菌の活動を抑える
フッ素は虫歯菌の代謝を妨げ、酸の産生を抑える効果もあります。菌の働きを直接弱める点でも、虫歯予防に有効なのです。

フッ素は本当に安全?よくある誤解
インターネット上では「フッ素は毒だから危険」という情報も見かけます。たしかに、非常に大量のフッ素を一度に摂取すると急性中毒を起こす可能性があります。
急性中毒が起こる量:体重1kgあたり5mg以上のフッ素を一度に摂取した場合
例:体重20kgの子どもなら100mg以上のフッ素を一度に摂取
市販の歯磨き粉(フッ素濃度1500ppm、100g入り)には約150mgのフッ素が含まれています。つまり20kgの子どもが歯磨き粉1本近くを丸ごと飲み込むような状況でなければ、中毒の心配はありません。
普段の「米粒大」「グリーンピース大」といった適正量を使っている限り、安全に虫歯予防ができます。
フッ素濃度の新基準と使用目安
以前の日本では、歯磨き粉に含まれるフッ素濃度は最大1000ppmに制限されていました。しかし研究の結果、フッ素濃度は高いほど虫歯予防効果があることが明らかになり、2017年に日本でも上限が1500ppmに引き上げられました。
この改定により、欧米と同等の虫歯予防効果を期待できる歯磨き粉が一般家庭でも使えるようになったのです。
斑状歯(はんじょうし)のリスクについて
フッ素は安全ですが、長期間にわたって過剰に摂取すると「斑状歯」と呼ばれる状態になる可能性があります。
起こりやすい時期:歯が作られる生後6か月〜8歳頃(特に1歳半〜3歳頃の永久歯前歯の形成期)
リスクが上がる摂取量:体重1kgあたり0.05〜0.07mg以上を毎日続けて摂取した場合
例:体重15kgの子どもなら、毎日0.75〜1.0mg以上を継続して飲み込むとリスクが増える。
歯磨き粉1000ppmの場合
米粒大(約0.1g)=約0.1mgフッ素
グリーンピース大(約0.25g)=約0.25mgフッ素
この量を毎日まるごと飲み込み続けると、斑状歯のリスクが高まります。一方で、正しく吐き出していれば心配はいりません。

年齢ごとのフッ素の正しい使い方
フッ素は年齢や歯の状態に応じて適切に使うことで、虫歯予防の効果を最大限に発揮します。ここでは、年齢ごとの使い方の目安をご紹介します。
幼児(0〜5歳)
- 使用濃度:1000ppm以下
- 使用量:
2歳頃までは「米粒大」
3〜5歳頃は「グリーンピース大」 - ポイント:幼児期はうがいが難しく、歯磨き粉を飲み込んでしまうことがあります。必ず保護者が仕上げ磨きを行い、誤飲を防ぎましょう。
学童期(6〜14歳)
- 使用濃度:1000〜1500ppm
- 使用量:歯ブラシに「1cm程度」
- ポイント:永久歯が生えそろう大切な時期です。虫歯リスクが高いため、適切な濃度のフッ素入り歯磨き粉を使うことが効果的です。
成人(15歳以上)
- 使用濃度:1500ppm
- 使用量:歯ブラシに「1.5〜2cm程度」
- ポイント:成人では虫歯予防はもちろん、知覚過敏の予防・改善にもフッ素が有効です。毎日の使用で歯の強化につながります。
高齢者
- 使用濃度:1500ppm
- ポイント:加齢により歯茎が下がると、歯の根元が露出し、虫歯になりやすくなります。フッ素を取り入れることで根面の虫歯予防が期待できます。
このように、年齢や生活習慣に合わせたフッ素の活用が大切です。お子さんから高齢の方まで、ご家庭での歯磨きにフッ素を取り入れ、定期的な歯科健診とあわせてお口の健康を守りましょう。
効果を高めるための使い方のコツ
- 歯磨き後のうがいは1回だけ(少量で)
- 寝る前の使用を大切に
- 毎日継続することが重要
- 歯科医院での高濃度フッ素塗布をプラス
まとめ
フッ素は、再石灰化を助け、歯を強くし、虫歯菌の働きを抑える成分です。
これまでは、日本小児歯科学会などが示す推奨濃度が全体的に低めに設定されていました。しかし近年、国際的な基準や最新の研究結果を踏まえ、年代ごとに推奨されるフッ素濃度が見直されています。現在では、幼児期にはおおよそ1000ppm前後、学童期には1000〜1500ppm、成人や高齢者には1500ppmと、年齢やお口の状態に合わせた使い方が推奨されるようになりました。これにより、より効果的に虫歯予防を行いやすくなっています。
ただし、1歳半〜3歳頃の永久歯形成期に、毎日大量に飲み込む習慣があると斑状歯のリスクが上がることも事実です。
使用量を守り、仕上げ磨きで保護者が管理すれば、フッ素は効果的な予防法です。迷ったときは、年齢や生活習慣に合わせたフッ素の使い方を、歯医者さんにご相談してみましょう。
長崎県諫早市永昌東町16-28 2階
医療法人 夢昂会 諫早駅前歯科
📞 電話番号 0957-46-7700
インスタグラムや公式ラインからの相談もお待ちしております。