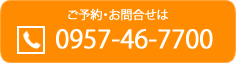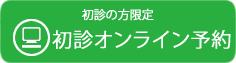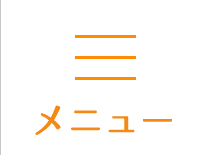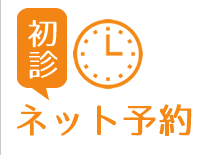こんにちは、長崎県諫早市の歯医者 諫早駅前歯科です。
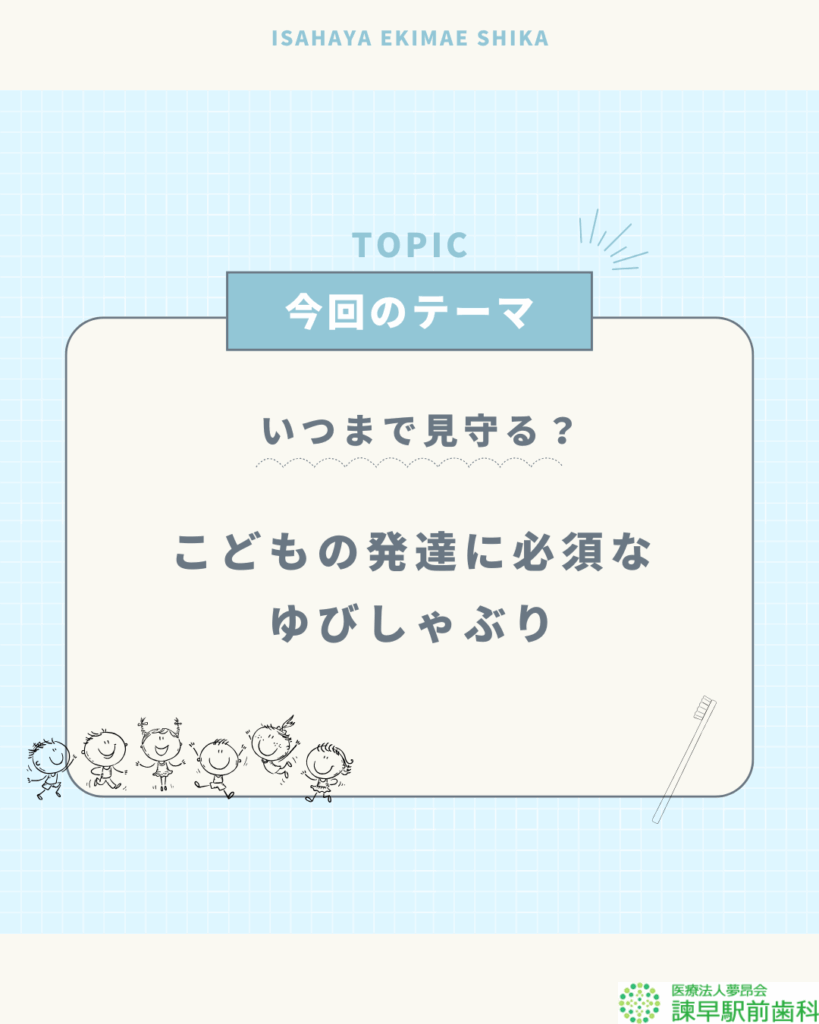
今回は、小さなお子さんを育てる保護者の方からよく寄せられる「指しゃぶり」に関するご相談について、歯科的・心理的な観点からわかりやすくご紹介します。
目次
指しゃぶりは悪いこと?それとも必要なこと?
赤ちゃんの指しゃぶりは、ごく自然な成長過程の一つです。生まれてすぐの赤ちゃんは、口を通して世界を知ろうとする本能があり、不安や空腹、眠気などを感じたときに自分を安心させる手段として指しゃぶりを行います。とくに0歳〜2歳ごろまでは、生理的な欲求に基づく行動として、ごく一般的なものと考えられています。
ですので、この時期の指しゃぶりを「やめさせなければ」と過度に心配する必要はありません。むしろ、子どもが自分の力で安心を得る大切な手段として尊重する姿勢が大切です。
いつから注意すべき?年齢によって変わる意味
指しゃぶりの意味は、年齢とともに変化します。3歳以降になると、指しゃぶりが心理的な不安のサインである可能性が高くなります。
たとえば、弟や妹の誕生や保育園・幼稚園などの環境変化、親との関係でさみしさを感じることなどがきっかけになることがあります。このような年齢での指しゃぶりは、単なる癖ではなく「不安を伝える行動」でもあるのです。
そのため、単に「やめなさい!」と叱るのではなく、なぜその行動をしているのか、子どもの心に寄り添う姿勢が大切です。また、3〜4歳を過ぎても日常的に指しゃぶりを続けている場合には、歯並びや虫歯になりやすさにも影響が出る可能性が大きくなるため考慮する必要が出てきます。
指しゃぶりが歯や口に与える影響
・開咬(かいこう)
上下の前歯が噛み合わず、すき間ができたままになる状態です。食べ物を噛み切ることが難しくなるほか、発音にも影響が出ることがあります。
※開咬に関する過去の記事はこちら
・上顎前突(出っ歯)
上の前歯が前方に押し出され、出っ歯の状態になることがあります。口が閉じにくくなり、口呼吸や唇の乾燥の原因にもつながります。
※上顎前突に関する過去の記事はこちら
・口唇や舌の機能低下
指しゃぶりによって舌の位置が下がったり、唇を閉じる力が弱くなったりすることで、「ぽかん口」や発音の問題が起こることがあります。
無理にやめさせない。でも放置もしない。
3歳を過ぎても続く指しゃぶりは、徐々に卒業を目指す時期です。しかし、大切なのは「無理にやめさせようとしない」こと。実際、無理にやめさせると、指しゃぶりの代わりに爪噛みや赤ちゃん返りなど、別の行動で不安を表現するケースもあります。
ここで参考になるのが、保育の現場でも支持されている方法です。
たとえば、指しゃぶりをしている時に、そっと手を握って「おてて大きくなったね」と声をかけてみたり、一緒に新聞をちぎったり、折り紙をしたりと、両手を使う遊びに誘導してみるのもおすすめです。
また、寝る前の指しゃぶりには、添い寝をして手をつないであげると、お子さんは安心して眠りにつくことができます。
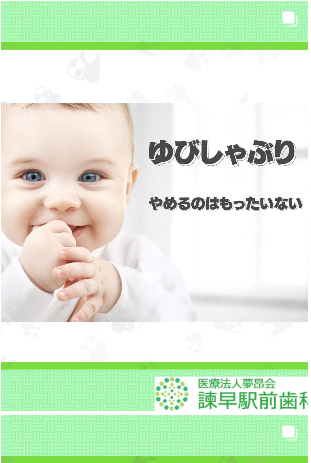
卒業をサポートする工夫いろいろ
次のような方法も、子どもが自然に指しゃぶりから卒業する手助けになります。
・小さな目標を決めて、シールやごほうびで達成感を育てる
・絵本『ゆびたこ』などで、行動の意味を理解する
・苦味成分入りのマニキュア(カムピタ+)を活用する
・指しゃぶり卒業キットや表彰状を取り入れる
これらの方法は、子どもの年齢や性格に応じて使い分けましょう。
パパママができる毎日のサポート
指しゃぶりの背景には、不安だけでなく「退屈」や「手持ち無沙汰」も関係しています。
・会話やスキンシップの時間を増やす
・寝る前のルーティンを整えて安心感を高める
・手遊び歌やブロック遊びで手を動かす時間を増やす
といった工夫で、指しゃぶりをする場面自体を減らすことができます。
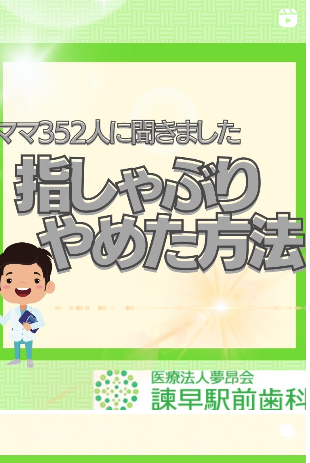
よくあるQ&A
Q. 妊娠中ですが、おなかの中の赤ちゃんも指しゃぶりをしますか?
A. 超音波検査で、おなかの中の赤ちゃんが親指をしゃぶっている様子が確認されることがあります。これは口唇の感覚を育て、出生後の授乳動作の練習にもつながる大切な行動です。
Q. 指しゃぶりが原因で矯正治療が必要になることはありますか?
A. 開咬や上顎前突が固定化すると、将来的に矯正治療が必要になる場合があります。永久歯が生えそろう前にやめられれば、自然に噛み合わせが改善するケースも多いので、まずは6〜7歳頃までの卒業を目標にサポートしましょう。
ワンポイントアドバイス
3か月おきに定期検診を受け、噛み合わせや口腔機能をチェックしましょう。必要に応じて、保護用マウスピースなどを提案することもあります。
言葉での表現が未熟な幼児期は、生活リズムの乱れや家族の変化などが指しゃぶりに現れやすい時期です。日記やメモで「いつ・どこで・どんな場面で」指しゃぶりが起きるかを記録すると、サポートのヒントが見つかります。
ママパパ自身の心構え
子どもの癖を直すには、どうしても大人の根気と時間が必要です。
・完璧を求めず、できた日を一緒に喜ぶ
・「ダメ!」より「こっちにしようね」と提案型の声かけをする
・保護者同士・祖父母とも情報共有して、一貫した対応をとる
といったポイントを意識すると、子どもは安心して行動を変えることができます。
こんなときは相談してみてください
次のサインが見られたら、早めにご相談ください。
・前歯がかみ合わず麺類が噛み切れない
・唇を閉じると下顎に梅干しジワができる
・寝ている間に口が開いている、いびきをかく
・4歳を過ぎても指しゃぶりを頻繁にしている
歯科医師と一緒に、噛み合わせだけでなく呼吸や姿勢まで含めた総合的なサポート計画を立てましょう。
まとめ:指しゃぶりは「成長のサイン」でもある
指しゃぶりは、子どもにとって「心のSOS」のようなもの。やみくもに止めるのではなく、その背景にある気持ちに寄り添い、環境や関わり方を見直すことで、自然と卒業できることも多いです。
そして、長引く場合には歯並びへの影響も考慮し、必要に応じて歯科医院へご相談ください。
諫早駅前歯科では、お子さん一人ひとりの発達に合わせたやさしいアドバイスを心がけています。気になることがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。
長崎県諫早市永昌東町16-28 2階
医療法人 夢昂会 諫早駅前歯科
📞 電話番号 0957-46-7700
インスタグラムや公式ラインからの相談もお待ちしております。